鎌倉五山第3位の「寿福寺(じゅふくじ)」は臨済宗建長寺派のお寺で、鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」の妻「北条政子」、その子供「源実朝」のお墓があることで有名です!
また、頼朝の父「源義朝」の居館があったことや、古くは、後三年の役(1083年~)の活躍で知られる「源義家」などと所縁のある、源氏伝来の地として知られます。
鎌倉「寿福寺」は、「源頼朝」が亡くなった翌年、妻である「北条政子」が菩提を弔うため正治2年(1200年)に「栄西」を開基として創建しました。
鎌倉「寿福寺」を参拝される方は、その昔、鎌倉五山第1位の「建長寺」に劣らぬ規模だったとされる「海蔵寺」や、金運アップの「銭洗弁天」も一緒に観光するのがオススメです!!!
参拝のポイント↓↓↓
総門から本堂に向かう「参道」は息をのむ美しさ
鎌倉幕府を開いた「源頼朝」の妻「北条政子の墓」がある
その子供「源実朝」のお墓もある
「本堂」奥の境内は非公開
ゴールデンウィークやお正月には「特別公開」がある
「鎌倉駅西口」からアクセス!

JR鎌倉駅に着いたら西口改札にでます。
東口ではないので要注意です。

鎌倉駅西口を出て正面の通りをまっすぐ行くと、「紀ノ国屋」がある「市役所前」交差点に出ます。
「市役所前」交差点を写真↑↑↑右方向に10分ほど歩けば「寿福寺」へ到着します。ちなみに真っ直ぐすすむと金運アップの「銭洗弁天」や鎌倉アルプスを一望できる「源氏山公園」などへ行くことができます!
駐車場や拝観料は???
寿福寺に参拝用駐車場はありません!近隣のパーキングを利用して下さい→「寿福寺近隣のパーキングはこちら」
参拝料はありません!
特別公開の日は拝観料があるようです。今後調査して追記します。

途中には鎌倉幕府ともゆかりの深い武将「相馬師常」が建立した「八坂神社」がありますので、一緒に参拝してみてください!
「総門」

鎌倉駅西口から10分ほどで「寿福寺」へ到着しました。この山門から本堂までの参道がすごく良い感じ。
「寿福金剛禅寺(じゅふくこんごうぜんじ)」とあります。

木々の隙間から木漏れ日がさしてきて大変美しい。境内には鎌倉幕府初代将軍の妻「北条政子」の墓があります。
「美しい参道」

「北条 政子」
「北条政子」は鎌倉幕府の祖、「源頼朝」の正室でした。
静岡県伊豆地方の豪族であった北条時政(ほうじょうときまさ)の長女として生まれました。
当時北条家は源頼朝の監視役を務めていたようです。
しかし、頼朝と政子は互いに慕いあう仲となってしまいました。
周囲は大反対したようですが、最終的には流人だった頼朝の妻となってしまいました。
鎌倉幕府が成立し武家政権を発足すると政子は御台所と呼ばれるようになりました。
1199年に頼朝が亡くなると征夷大将軍となった長男頼家、次男の実朝が連続して暗殺されてしまいます。
その騒動後は、京から招き将軍とした幼い藤原頼経(ふじわらよりつね)の後見人として幕政の実権を握り、尼将軍とよばれるようになったそうです。
「紅葉」

頭上に目をやれば、太陽の光に照らされた木々が美しい色彩を放っています。
ちょうど紅葉だったので、燃えるような赤色が拝めました。寿福寺周辺の路地裏も良い感じでした。

紅葉がまだまだきれいでした。(12月上旬)
「非公開」の「本堂」

寿福寺は観光客が入れるのはこの本堂前の山門前までです。
本尊は「釈迦如来」本堂内には源実朝の像が安置されています。「釈迦如来」を本尊に持つ鎌倉のお寺は北鎌倉の「円覚寺」や浄妙寺・十二ヶ所エリアにある「報国寺」などがあります。
他のお寺に比べると見学時間はあっという間で終わってしまいます。
5月の第1週やお正月には特別に境内が公開されるそうです。まだ拝観したことがないので潜入調査して来たいと思います!
しかし!この山門と本堂のあいだの参道だけでも来る価値があると思います!!!
鎌倉のお寺の中でもトップクラスの雰囲気の良さだと私は思っております!!!
とにかく木漏れ日と木々が美しく、空気が抜群に良いです。紅葉がちょうど見ごろでラッキーでした。
北条政子の墓、鎌倉「寿福寺」の歴史

「寿福寺の歴史」
鎌倉「寿福寺」は「鎌倉五山」第3位のお寺です。
山号は「亀谷山(きこくさん)」臨済宗建長寺派のお寺です。
上の写真にもあったように正式には「寿福金剛禅寺(じゅふくじこんごうぜんじ)」
本尊は「釈迦如来」をまつっています。
寿福寺の創設者は頼朝の妻である「北条政子」、開基である初代住職は「栄西」です。
鎌倉三十三観音霊場の第24番目。
鎌倉二十四地蔵の第18番目となります。
境内は「寿福寺境内」として1966年に国の史跡に指定されています。
鎌倉幕府初代将軍の「源頼朝」の父である「源義朝」の住まいがあった土地だそうです。頼朝が平家との戦いに勝ち鎌倉に舞い戻ったときに、この地を幕府の中心とするつもりだったそうです。
しかし、父義朝の時代から長年の部下であった「岡崎義実」がお堂を建て義朝の菩提を弔っていた。さらには土地が狭かったこともあり当初の計画を変更したということです。
創建当時は「七堂伽藍」が立ち、14の塔頭(たっちゅう)を持つ大きなお寺でした。
寿福寺が禅のお寺になっていったのは1278年ころと推定されているそうです。
1247年に火災にあい、1258年にも火災があってお寺のすべてが焼失してしまいました。
その後、寿福寺が再興されたのは南北朝時代の頃とされています。
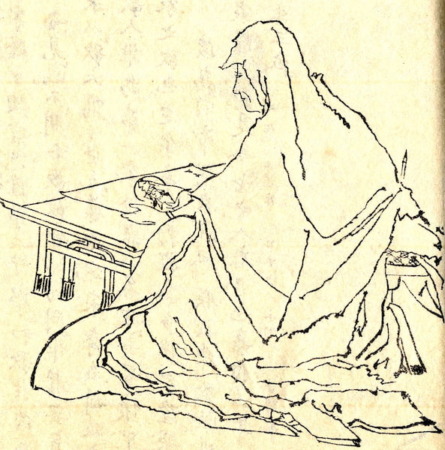
みどころまとめ

最高です。
「寿福寺」は、ちょっとしか見れる場所がないにも関わらず、その空気感だけで個人的に鎌倉のオススメトップ寺院となっています。
見るものがないとダメな人にはおススメできません。
しかし、空気に触れて見えない何かを感じる方には最高の場所ではないでしょうか!ぜひ大きいお寺だけでなく、こういう場所も楽しんで欲しいです。
「寿福寺」境内にある「北条政子」の墓は見学できないと思っていましたが、寿福寺の裏山に、鎌倉特有の「やぐら」形式として安置されている様です。
一緒に鎌倉幕府第三代将軍の源実朝のお墓もあるようです。
この寿福寺の地は、頼朝より昔に祖先である「源頼義」が勝利を祈願したとされる「源氏山」を背にした、亀ヶ谷と言う源氏ゆかりの地だそうです。
「源頼朝」の父、源義朝の屋敷もここにあったそうで、頼朝は鎌倉幕府を開くにあたり、本拠地をここを考えていたと言われています。
この場所が手狭であり、すでに「岡崎義実(おかざきよしざね)」が源義朝の菩提を弔う施設を作っていたこともあり、大倉幕府の場所にしたそうです。
後日再訪し写真を撮れたら撮って来たいと思います!!!
参拝のポイント
総門から本堂に向かう「参道」は息をのむ美しさ
鎌倉幕府を開いた「源頼朝」の妻「北条政子の墓」がある
その子供「源実朝」のお墓もある
「本堂」奥の境内は非公開
ゴールデンウィークやお正月には「特別公開」がある

鎌倉「寿福寺」基本情報
住所 〒248―0011 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-17-7
電話番号 0467-22-6607
定休日 ありません
拝観時間 特になし
拝観料 無料(仏殿公開時は拝観料が必要)
駐車場 ありません
アクセス JR横須賀線「鎌倉駅」西口を出て右手に線路沿いを進みます 徒歩約10分くらい

コメント